証
見渡す限り動くものは何もない。いくつも転がっているひとがたは最早ただの容れものでしかなく、その中身はすべて空だった。頬に当たる風は止み、死肉に目敏いはずの鳥たちもまだ姿を現さない。
上体を起こした戸部は目の前の骸を一瞥した。眼は此方を睨んだまま、口は叫び声の形に開いたまま時が止まっている。その腹からずぶり、と愛刀を引き抜けば鏡のようだった面は血と脂が固まって、もはや刃というより鈍器だった。体力の消耗と切れ味を失った刀のせいで、最後だけは振り抜けなかった。男は突きだされた戸部の刀を胎内に呑み込んだまま絶命した。
のろのろと辺りを見渡せば、同じようにかつてひとだった物が、思い思いの格好でやはり戸部を見据えていた。空気の流れさえ沈黙しているこの場で生きているのは己だけだ。いや、今この身が彼らの仲間ではないとどうして言えよう。数え切れぬほど太刀を受けたはずなのに痛みすら感じず、身を覆う血は返り血なのか出血なのか判然としなかった。もう己は死んでいて、今ある意識はまやかしなのではないか。指ひとつ動かすことすら重いのは、もう完全に動かないからかもしれない。急に座る地面が頼りなく沈みゆくように感じて、ゆるゆると瞼を閉じかけた時。
ぐぅるるるるるる、と場違いな音が響いた。
ああ、己は腹が減っているのだ。死線を潜りぬけて、暢気にも腹を空かせている。生きている。己はまだ生きていた。
喉からふふふ、と笑いがこみ上げて、力の入らぬ腹を抱えて戸部は笑った。笑いは雲ひとつない青空に吸い込まれ、そうして戸部は笑いながら意識を手放した。
山道は太陽が葉を透かし、時折驚いた小鳥が鋭く囀る。葉を揺らし下草を踏みながらさんざめいて跳ねるように歩くのは、一年は組の福富しんべエと山村喜三太だ。彼らの護衛兼お守りを言い遣った戸部はその少し後ろから、足音ひとつ立てずについてゆく。
子ども特有の甲高い声が昼前の穏やかな林に響いて、葉の上の露を滑らせる。その裏に蛞蝓を見つけるたびに歓声が上がって、子どもの結髪がぴょこんと跳ねた。そのいかにも子どもらしい無邪気な様子は金吾とはまた違っていて、集団としての1年は組は見慣れているはずの戸部にとっても新鮮であった。
彼らが目指すのは陶芸の名人の庵である。なんでも、しんべエと喜三太がアルバイトに行きひどく気に入られたとかで、今回学園長にその名人から、良い茶碗が焼き上がったので差し上げたい、ただし受け取りに来るのは福富しんべエと山村喜三太であること、という書状が届いたのだった。
折悪く担任の土井は恒例の胃痛で寝こんでおり、山田は他の用事で学園に詰めていなければならない。共にその名人を訪ねたという六年い組の立花を含む上級生たちは、あらかた任務中か先手を打って街に行ってしまった後だった。そしてなぜか戸部に彼ら二人のお守りが回ってきたのだ。
「戸部せんせー」
まだ声変わり前の、間延びした独特な声が戸部を呼ぶ。
「どうした喜三太」
「あれなんですかー?」
小さな指が示した先には、親指ほどの大きさで、真っ赤な人の手のようなものが木の根から生えていた。
「あれはカエンダケという。橙色で枝別れしているから火のように見えるだろう」
「ほええ、綺麗な色」
「見るのは良いが、毒キノコだ。触るだけでかぶれるとも聞く。手を出すんじゃないぞ」
「はーい」
「せんせー、おなかが空きましたぁ」
「さっき朝餉を食べたばかりだろう」
「でも、背中からおにぎりの匂いがして……」
「今食べたら昼の分が無くなるぞ。我慢しなさい」
出かける時、食堂のおばちゃん特製の特大おにぎりが喜三太やしんべヱには二つずつ、戸部には三つ用意されていた。いい年になって、ちゃんと食べるんですよと母親のような注意を長々と受けた戸部は、早く逃げたい一心でそれを風呂敷に押し込んで来たのだ。
気がつけば喜三太の姿が見えない。まさかと思って辺りを見渡すと、右手一帯の子供の背のたかさほどある笹やぶの中に、ふわふわとした茶色いまげが突き出しているのが見えた。あわてて自身もやぶの中に入ったとたん、目印のまげは消えてしまい、内心焦りつつもともかくやぶをこいで先程見当を付けたあたりに向かう。戸部の腰の上まである笹はこの時間朝露に濡れていて、装束は色が変わるほど湿ってしまった。
「喜三太!返事をしろ!」
「はにゃ」
いきなり左耳のすぐ後ろで声がして、ぼさぼさのまげがぴょこんとやぶの上に現れた。動くなと言い置いて、細い笹の枝をかきわけると、ようやくナメ壺を抱えた喜三太が見えた。一年生の彼の背では、しゃがんでしまえば完全に笹に隠れてしまっただろう。
「喜三太!」
「ナメさんが逃げちゃって、追っていたらどっちからきたか分からなくなっちゃったんですー」
ほっとした戸部はその泥だらけの手を握って、自らのやぶこぎの跡を辿って本道に戻る。たしかに子供が弱い力で笹をすりぬけるように進んだ跡では、すぐに笹は元通り閉じてしまう。喜三太は視界の効かない中迷ってしまったに違いない。
本道に戻ってみれば二人を追いかけようとしたのだろうか、今度はしんべヱが笹やぶに半分埋没していた。
ただし戸部にとっては幸いだったことに、しんべヱの髪やら服やらには笹がひっかかりそれ以上の侵入と身動きを阻んでいるようだ。こうして半分泣きべそをかくしんべヱをなだめながら絡みついた笹を外してやる頃には、戸部まですっかり泥と笹の葉でぐちゃぐちゃになっていたのだった。
頭の先から足の裏まで泥だらけ、草の匂いをまとった三人を太陽の熱と光が乾かしていく。こびりついた泥はあっという間に白くなり、こすれば簡単に落ちた。初夏の日光のおかげで、露で冷えた身体もすぐに温まった。ただもう笹やぶは随分遠くなったというのに、あの甘いような笹の香りだけは熱に焙られた香のように三人を包んでいた。
峠を二つ越えた頃だろうか。ふと前を行く二人の子どもの足が止まった。顔を見合わせ何やら首を傾げている。
「どうした」
「それが……」
「たしかにこの辺だったと思うんですけど」
嫌な予感はするが、露骨に顔をしかめたくなるのを我慢する。
「名人の庵に通じる道の脇に、たかぁい柏の木が立ってたんです。僕たちそれを目印にすればいいや、って、思ってたんですけどぉ…」
先日季節外れの嵐があって、学園も随分と雨風を感じたものだが、このあたりはさらに被害が酷かったらしい。少しでも幹が弱っているものは軒並みなぎ倒されて、すっかり日当たりがよくなっている。随分と風景が変わっている上に、柏はこの一帯では珍しくもない木である。要は三人揃って迷子というわけだ。
「森の中で木を目印にするのは危ないと習わなかったか……。なにか他に覚えていないのか」
「んーと、木の根元に、蛙の形をした石があったような気がしますぅ」
大きさを尋ねれば、このくらいと言ってしんべえが小さく手を動かす。戸部の両手に載るくらいの大きさらしいそれが、この倒木と落ち葉だらけの地面の中で見つかるかと気が遠くなったが、とにかく三人で手分けして探すことにした。ただし姿が見える範囲にしろと念を押すのは忘れない。
柏らしき倒木を見つければ苦労して細い丸太をどけ、腰を屈めて石を探すもののやはりなかなかそれらしい石は見つからない。その時、本道から少し離れた沢に、戸部は人の姿をみとめ降りて行った。地元の人間であればなにか知っているかもしれない。
どうやら初老の男がひとり渓流釣りをしているようだ。早速近づき、もし、と声をかけた。
「何だね」
「物をお訊ねしたいのだが、この近くに陶芸の名人が住んでいる庵をご存じか」
「ああ、なんだあの爺さんのお客さんかい」
そう言って男は竿を置いて立ち上がり、沢の斜面を登った。
「こちとら日の明けねえうちから釣り糸を垂らしてるんだが、まったくこの頃はついてねえ。おかげでもう丸一日、碌なもんを腹に入れてねえから腹が鳴って困るよ。魚が音で逃げちまう……っと、あれだ、見えるかい、あの山の尾根に三つ並んだ岩が見えるだろう。爺さんの庵はあの右っぱしの岩の根元だよ。そこにうっすら獣道みてえな跡があるだろ、こいつを辿ってゆけば迷わず行けるよ」
本道に立って指し示された辺りを見れば、確かに無残に折れた一本の根元に、鹿が踏みしめたようなかすかな跡がある。戸部は丁重に礼を言った。
「なにか差し上げられればよいのだが」
「そんならお侍さん、あんた食い物持ってるんだろう」
「それは」
「山の中で飢え死にしそうになってるってのに、銭なんぞもらったところで何の役にも立たねぇや。そいつをくれりゃあもうちっと沢で頑張る気になるってもんだ」
こうして戸部は風呂敷包みを解き、三つの特大おにぎりのうち一つを男に与えたのだった。
男が沢に戻ると同時に、しんべえ、喜三太が折よく戻ってきた。三人で例の柏の下を覗いてみれば、たしかにほどよい大きさの岩が転がっていて、それをひっくり返せば座った蛙に見えなくもない。
「行くぞ」
「「はーい」」
明るい声が重なった。
こうして途切れがちの踏み跡を辿ること半刻。日が高く上がりきった頃、斜面を切り開いた作業場と粗末な小屋が木々の間に見えた。ここまでくると現金なもので、散々疲れただの足が痛いだの言っていた子どもたちは、歓声をあげて小屋に駆け寄っていく。よほど陶芸の好々爺に懐いているらしい。
案の定、木戸を開けて彼らを迎えた老人からは目を細めて歓迎された。三人は小屋の奥に通され、茶を出され、それどころか驚いたことに、老人は子ども二人に土をこねてくれと懇請するのである。付き添いの戸部が作業場に入ることを許されず外の木陰で待つ間、老人の感心する声がひっきりなしに響いてくる。
とはいえ待つ身としては暇を持て余し、作業場の周囲をひとまわりしてみることにした。粗末な小屋はどうやら、近くの木を適当に切り倒して作ったようだ。小屋の周りには一本の桜の木を除いて高い木はなく、背の高いうどのような野草や、細いひこばえが足の踏み場もないほど雑然と生えている。その一角の山吹の茂みに近づいた時、視界の端でちょろりと動くものがあり、武芸者の常として瞬時にそちらに意識が向いた。
何のことはなく、やせ細った子ダヌキが一匹、茂みの下から顔をのぞかせているだけである。
人間がいるというのに逃げもせず丸い目でこちらを見上げてくる動物がなんとなく気になって、屈んで茂みの下を見ると太めの枯れ枝のようなものが落ちている。否、よく見ればそれは横向きに倒れたタヌキで、細い前足をだらりと突きだしている。
その獣は不躾な人間に気付いて、ようよう鼻面をちょっと動かして威嚇らしき声を出した。その腹のあたりには、親や兄弟に負けず劣らずやはり小さく細い子ダヌキがもう一匹、しきりに顔を親の毛皮に押し付けていた。
最初の子ダヌキが戸部の足元まで出てきて、ふんふんと匂いをかいで体を右足にすりつけた。甘えるような声を出す。
「なんだ、お前たち腹が減っておるのか」
くぅん、と子ダヌキが鳴く。
その切なげな声と視線に抗い切れず、残り二つの握り飯のうちひとつを子ダヌキの横に置いてみる。すると子ダヌキはそれを器用にくわえ、母親の口元へ運ぶではないか。
握り飯を分けあって食べるタヌキの親子を見ているうちに、作業場のほうで喜三太が彼を呼ぶ声がした。
結局、顔や手足に土をつけたしんべヱと喜三太を従えて、例の茶碗を携えて戸部が庵を出たのは中天を通過した日がだいぶ傾いた時分だった。子ども二人は菓子をもらってご機嫌らしい。ぷくぷくとした笑顔で声も高くはしゃいだ足取りである。
その機嫌の良さはしかし長くは続かず、例の蛙石の分岐を過ぎた頃しんべヱの足が鈍りだした。時をおかず喜三太も口数が少なく遅れがちになる。戸部が気付いて足を止めたとき、しんべヱの腹の虫が大きく鳴った。
戸部はなだめすかして二人をもう少しだけ歩かせ、倒木だらけの林を過ぎ見晴らしの良い峠に出たところで、昼食をとることにした。
よほど腹が減っていたと見えて、野原に適当に腰を下ろすなりしんべヱはもう満面の笑みでいそいそと風呂敷包みを開く。喜三太もその隣で自分の風呂敷を広げ出した。
戸部自身も大分軽くなってしまった風呂敷を降ろし、まずは水筒で喉を潤した。それから竹の包みを開いて、残りひとつだけになった握り飯に手をかけた時、しんべヱの高い悲鳴が響いた。ぎょっとしてそちらを見ると、しんべヱの伸ばした手の先に、斜面を転がり落ちてゆく白い塊が見えた。
それほど急な斜面とは思わなかったのに、握り飯はあっという間に草の間を抜け、岩の上で大きく一度跳ねて見えなくなった。たしかあの下は崖で、谷川が流れていたはずだ。
喜三太が必死でしんべヱを慰めようとするのだが、しんべヱは座りこんで呆然と握り飯の消えた先を見つめている。戸部はため息をついた。
「しんべヱ、見たって戻らないものは戻らんぞ」
「とべせんせぇ」
すでに泣きべそが混じっている。悲しさが伝染したのか、喜三太の大きな目まですでに潤み始めていた。
「私のをやるから、これでよいだろう。泣くなしんべヱ、喜三太も大丈夫だ」
「でも……」
一年は組一の食いしん坊と言えど、戸部の体質を知っていると受け取るのに躊躇するらしい。二人は顔を見合わせている。十の子どもに腹の具合を気遣われるのも情けない。もう一度促してやると、しんべヱがおずおずと手を伸ばした。しかしなおも戸惑ったように戸部の顔を見る。
「先生がお腹空いちゃう」
「私は元々三つ頂いていたのだ。大丈夫だから、食べなさい」
「けど先生、残り二つは」
「……さっきお前たちを待っているときに食った」
先に食べちゃうなんてずるい、という声に明るさが戻って、どうしようもなくほっとした己に驚く。ともかくしんべヱと喜三太は気持ちのいい勢いでふたつの握り飯を咀嚼してゆく。行きの時間からして、あと一刻半ばかりもあれば学園に着けるはずだ。夕飯にはまだずっと早いが、学食のおばちゃんに頼んで何か食べさせてもらえばいい。
そう計算した戸部は、手元の水筒の水を一気に煽った。
だがその計算が甘かったことを、彼は身をもって知ることになる。子どもの足は戸部の思ったより遅く、また疲れやすいようだった。早朝から歩き続けてきたしんべヱと喜三太は時折休憩させてやらねば歩けなかったし、行きはなんでもないように下ってきた斜面が登るとなると一苦労だったりした。
ぐずる喜三太をおぶって少し歩き、さらにはそれを羨ましがったしんべヱと交代させ、背中の重みでますますよろけそうになる足を叱咤激励しながら歩いた。子どもの体は小さいようでいて、見た目よりずっと重い。成長途中の臓器や骨がしっかり詰まっているのだろう。だがくたりとやわらかくのしかかる体重は、不思議と圧迫感を感じさせなかった。どちらかを背負っている間中、戸部は押し入れの中で湿気を吸った、季節外れの綿入れを思い出していた。幼いころ彼はそのぼろぼろになった綿入れに包まるのが好きだった。
いつしか戸部は二人の手を握り、三人は並んで山道を歩いていた。折からの斜陽に木の影がひょろりと長く伸び、葉の縁がきらきらと輝く。この峠を越えれば忍術学園が見えてくるはずだ。風が吹くたび腹に切なさを感じるのを気のせいだとしてきたが、実はそろそろ限界も近い。
ぎゅっ、としんべヱが戸部の右手を強く握った。ふくふくとした丸い手は、戸部の骨ばった手の中で大福餅のように白く見える。わずかに足がよろけたのに気付かれたかと顔を見れば、先程までの泣き顔が嘘のように、夕陽を眩しがりもせず眉をきっと寄せて前を見据えていた。戸部を介して意識が伝わったかのように、喜三太もやはり勇ましく着実に坂を上っている。今や戸部が二人を引っ張っているのか、二人が戸部を引っ張って歩かせているのか分からなかった。
ふと耳の後ろに気配を感じた。
素早く足を止め、しんべヱと喜三太の手を離して愛刀の位置を確認したと同時だった。果たして左右の藪が揺れて、十人ほどの身なりのよくない一団が現れた。
「やれやれ、やっと見つけた獲物だが碌なモンは持ってそうにねェなあ」
「お前ら、餓鬼どもは殺すなよ。いくらでも売りようはある」
泥に汚れた下品な顔をにやつかせる男が彼らの首領だろうか。良くも悪くもこういうシチュエーションになれているらしいは組の二人は、戸部の後ろに隠れながらも憤然と懐を探っている。どうせ武器でも捜しているのだろうが、こういう時に限ってなにも持っていないのがお約束だ。
戸部は二人を片手で制し、小声で言った。
「走れ」
「でも…」
「走れ。学園はまっすぐ先だ。決して振り返らず、止まらず走れ。戻ってきたらお前たちでも斬る」
この場で、この腹具合で、一年生二人を庇いつつ十人の盗賊を相手にするのは避けたかった。負ける気はしないが、一年生には毛筋ほどの傷も付けたくは無い。
低い声と気迫に押されたのか、後ろで二人が頷く気配がする。
一番前の盗賊が一歩前に踏み出したその瞬間、
「走れ!!!!!」
戸部の号令で一目散に、というよりは若干もたつきながら、しんべヱと喜三太は走り出した。
慌てて距離を詰めようとする盗賊を刀の一閃で峰打ちにする。
「ここから先には行かせぬ。あの二人を追いたくば、私を仕留めてからにしろ」
言葉もなく鉈を振りかざして迫る盗賊をひらりとかわし、返す刀で背を打つ。かと思えば下からつきあげるように鳩尾を狙う。右手の刀が受け止められれば、左手の鞘すら使う。戸部の剣術は流派に縛られない。それは彼自身が諸国を流れ歩いて修行するなかで、良いと思えば採り入れ真似して身に付けた「戦法」であり、大刀筋は二度と同じ軌跡を辿ることはない。翻弄された盗賊は次々と地に伏せる派目になった。
戸部が血の臭いをつけることをためらったために峰打ちを貫いたのは、盗賊たちにとっての幸運だったろう。まだ動ける者が気絶したものを引き摺り、ほうほうの体で退却する盗賊たちに言い放つ。
「ふたたびこの近辺で仕事をするなら、次は首が身体が離れるぞ。疾く去ね」
だが戸部にとっても、それが限界だった。
盗賊たちの姿が見えなくなった瞬間、ふらりと身体が傾いで傍の木に思わずもたれかかった。もう何度となく経験していたこの感覚。
(しまった)
先程の盗賊たちがもし万が一戻ってきたらまずいことになる。それは分かっているのだが、全身から力が抜けて目眩がする。一息ごとに体幹から気力が抜けて行く。ずる、ずる、と幹を伝ってその場に座り込んだ戸部の視界に、金色の光を纏った森がぐるぐると回った。
「…んせい、戸部先生!」
薄目を開ければ、見慣れた同僚の顔が驚くほど近くにあった。鼻が付きそうな距離に思わず跳ね起き……るつもりがやはり力が入らず、無様に崩れ落ちる。
「そんなに驚くこたないでしょうが」
「…や、まだ先生」
呆れた風に自分を見下ろす細い黒装束はほとんど闇に沈んでいて、時間の経過を嫌でも知らされた。
「しんべヱと喜三太が泣きながら、あんたが帰ってこないって言うもんだから来てみたら、やっぱりこんなところで行き倒れだ」
「…面目ない」
夜目の効く戸部には、この暗闇でも山田の表情が手に取るように分かって、ひたすら首を垂れるしかない。
「そんなことだろうと思って、おばちゃんに握っていただいたんだ」
ため息と共に渡された大きめのおにぎりを二つ、それこそ脇目もふらぬ勢いで腹に収めた。食い終わると多少元気が出て、ふらつきながらも立ち上がった差しだされた手を思わず払い除ける。その途端足元の根に躓いて、情けなくも肩を掴まれ助けられてしまった。
「さっきまで倒れていたお人が無理をしなさんな」
山田の声に苦笑が混じっている。口の中でもごもごと礼を言うと、不意に山田の表情が引き締められた。
「戸部先生」
「はい」
「あんた、握り飯は学校から持って行ったでしょう」
「……やってしまいました」
「あげた?」
「うむ」
はぁ、と盛大なため息が聞こえる。
「ご自分の体質を知らぬ訳ではあるまいに」
「……」
「何か理由があったのだろうとは思いますがね、戸部先生、」
ぐっと山田の声が低くなった。
「あんたのその体質で食わないのは自殺行為みたいなもんでしょう。うちは生徒に何をしてでも生きのびる術を教えてる。先生のあんたがそんなでは困る」
戸部はただ頭を垂れ、それをどう受け取ったか、ともかくも山田は表情を和らげた。
「まあとにかく、学園に帰りましょう。以降こんなことは無いように願いますよ」
山田の後についてすっかり暗くなった山道を辿りながら、戸部はぼんやりと頭を巡らせる。
己は生きる気が無くて食わないのではなかった。むしろ腹を空かせることは己にとっての生きる証左であり、生に直結している。あのときそう反論しようと思えばできたはずなのだが、そうしなかったのは反駁するのを潔いと思わないからだけではない。
なにかが引っ掛かって、声が出せなかったのだ。
剣の道に生きていた頃。独りで、いくら抱いても冷たい愛刀だけを友として、時には何日も誰とも会わず一言も喋らず山を彷徨った。腹が空けば木の実や干し飯を貪り食い、空腹と満腹の往復に時間の経過を感じていた。
それに比べて今はどうだ。同僚がいて、寝る場所があって、今日のようなことが無ければ三食飯が出る。なんて快適で、退屈で、張り合いのない日々。かつての己が見たら、腑抜けになったものだと笑われるに違いない。
それなのにどうしてこんなに満ち足りているのだろう。どうして学園に帰れることをこんなに嬉しく思うのだろう。
「喜三太としんべヱが全部話しておったから、きっと金吾に叱られますよ」
前を行く山田の声がわずかに笑っている。そういえばあの二人にも心配をかけた。
そう思ったとたん、先程から掴めるようで掴めなかったもやもやの正体が見えた気がした。
己に縋りつく暖かさ。小さな手の柔らかさ。戸部せんせい、と名を呼ぶ高い声。
思わず小さな頭に置いた手は、日差しを呑み込む髪の毛の熱に驚かされた。そしてまっすぐ向けられるあの笑顔。
刀を両手で抱えて走り寄ってくる、幼い弟子の姿も重なった。
嗚呼。
空腹に証を求めずとも、ここにあるではないか。
子どもたちに触れ、触れられること。あのはちきれんばかりの生命に日々出会うこと。
あの温かみも体重も、己がからだで受け止めること。
それが生きている証でなくてなんと言えよう。
藪を透かしてぼうと滲む学園の灯りに改めて腹が鳴って、山田がやれやれと笑うのが分かった。
自然と足が速くなる。
いざ帰ろう。子らの待つ園へ。
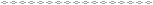
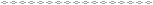
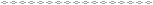
水谷の初恋は戸部先生でした。