その薄膜を突き破る、冷たくすべらかな質感について
宿題を教えてください、といって彼の人の部屋を訪ったのは、もう半刻も前になる。
障子を開けたら、狭い板間に色が溢れていた。山吹、金赤、常磐、薄紫、瑠璃紺、萌黄。それらはでろりと伸びた帯であり、畳まれた小袖であり、下げ緒であり、腰布の色であった。ちょうど外を染め上げている、木々の色づきにも余裕で勝る鮮やかさに、一瞬ほうっと当てられたようになる。
「なんだ、綾部か。入れ」
秩序も何もなくまぶしくひたすらに塗りつぶされた部屋の中で、ひと際沈んで見える深緑の忍着に身を包み、立花仙蔵その人は座っていた。
肩に流れる真っ黒な髪の毛が、妙に浮いて見えた。
結局宿題はそもそも基本のところで馬鹿馬鹿しいような思い違いをしていることが分かり、思い直して解いてみたら間もなく終わってしまった。用は済んだので帰ればいいのだが、何となくそう割り切った気分にもなれなくて、私は今もこうしてうだうだと板間にだらしなく寝転がっている。
秋は人恋しいとよく言う。
自室に戻った所で、同室の滝夜叉丸は今日も今日とて委員会で遅くまで帰ってこないだろうし、他の四年もこの時期はそれぞれに忙しい。要するに、今は独りぼっちと言う訳だ。今日のように素晴らしい天気の日には、いつもなら踏み鋤片手に単純であれど美しい労働にいそしんでもいいのだけれど、今日だけはなんとなく、自分の周りに別の気配があると言うのが心地よい。
もし秋に人は寂しさを感ずると言うのなら、私がここにこうして先輩の傍で寝転がったり、たいして意味の無い会話を時々交わすのだって、秋のせいに出来るのかもしれない。
私が広げてある着物をちょっとつまんだり、呆けた顔で天井の染みを数えて居ても、立花仙蔵先輩は文句を言わない。 まさか茶が出てくるわけではないけれど(噂では、六年は組の先輩方の部屋では自動でお茶が出てくる仕組みなのだそうだ)ただ放っておいてくれる。放っておかれた私はだから、先輩の背筋を正して書見台に向かうその後ろ姿を眺めたりする。
あちらこちらに極彩色の帯が伸びる空間の中で、先輩の完璧に結われた後ろ髪の帯はすっと床に直角に流れている。墨でひと刷毛はいたような、その律とした黒さだけが私の目に入る。
それでも段々と日は傾いてきていて、知覚できないほど次第次第に、部屋の彩度は落ちてきているようだ。
「先輩、これ、女装束ですね」
聞いたところで答えは明々白々なので、はじめから断定形で言った。
「ん?ああ、明日からの実習で使うと思って、広げて点検していた」
ちろり、とこちらを向いた肩ごしの目が、一瞬かち合う。髪の毛と同じ、絶対的な漆黒。
「実習なんですね」
「そうだ。…まあ、さして遠い所に行くでも無し、三日もすれば帰ってこられるよ」
「はあ」
なれば、今先輩が読みふけっている巻物は、実習先の機密でも書いてあるものか。
それから私たちはぼちぼちと先輩不在期間の委員会活動についてなどの話をする。とはいえもともとあまり忙しくない委員会であるし、こういう事務的なことはどちらかというと藤内の領分であるので(三木や滝夜叉丸にそう言ったら、四年としてそれはどうなんだと真顔で意見されたが、気にすることではない。誰にでも得意とする分野はあるし、こういう目端の必要なことが得意な藤内が、彼の得意分野で活躍できるのならとても喜ばしいことだ)話題はじきに尽きた。
先輩はまた巻物に戻り、私はぼんやりと部屋中にちらばった着物を見て回る。
淡い光沢のある淡黄色の地に山吹・常磐の緑・金赤などのさまざまな色で円い菊紋を散らした桂。その下に着られるであろう単は若草色のさっぱりとした立涌紋の総柄である。いつ着るのか分からないが、裾にいくにつれて紅の濃くなるように染められた裳袴もある。あちらには市女笠がなげだしてあり、薄い紗の白い垂れ衣の上に、緋色の懸帯がどぎついほどに存在感を示している。
部屋の中ほどには小物がまとめて置いてある。杏の地に白く浮かび上がる雪輪が刺しゅうされた錦の帯であるとか、色目も綾な藤や縹や朱の組み紐。どこぞの古着を仕立て直して作ったのだろう、丹念に刺しゅうのされた袋物。古いが造りのいいべっ甲やつげの櫛・かんざし。
「あ」
その中で私はつい、小さく声を漏らしてしまった。
手を伸ばして取り上げるのは、きらびやかな装飾品の中ではぱっとしない、艶消しされた鉄のかんざしだった。頭に簡略化された千鳥の形が打ちだしてあって、その先に小さな小さなざくろ石がなんだかもう縮こまって乗っている。
大きさは小さいが良質の石であるらしく、深いこっくりとした照りのある緋色の石が、無骨な黒鈍色のかんざし部分とはっとするような対照をなしているのだ。
「それの先には触るなよ、綾部」
巻物を読んでいるとばかり思っていた先輩が、いつのまにかたじろぐほどの真剣な目でこちらを見据えていた。
今やだいぶ日は傾いてきていて、西向きの部屋に入り込んだ光で、先輩の顔は朱色に反射している。
「なんでですか」
「先には毒が塗ってある。限界まで濃くした奴が」
だから下ろせ、と言外の圧力をかけられて、私は大人しくそのかんざしをそっと戻した。形のよい切れ長の瞳で言われるものだから、なかなかの凄みだ。ころり、と床に戻されたそれにも、真っ赤な夕日が差し込んできて、ざくろ石がぎらぎらと赤みを増す。血のようだ、なんて言ったら陳腐である。もっと、そう、これは先輩の胸の中で一分間に80回、几帳面に波打つ心臓の色。
私がきちんとそれを板間に置いて、手を離したのを見届けて、先輩はふっと口元を和らげた。
「前途有望な作法委員を、まさか私の部屋の中で失いたくはないからな」
幾分柔らかさの戻った口調でそれだけ言って、先輩はまた書見台に戻る。
頭の動きに合わせて髪がひとたば、さらりと優雅に舞った。
「どうして」
「…なんだ」
もうこの話題は終わりだ、と明らかにサインが出ていたが、私は我慢できなかった。
押せば案外情の通じる所のあるこの先輩は答えてくれる。
「どうして、毒なんか」
「おいおい、悟ってくれないか。四年なんだから」
「分かりません」
「またそんな」
「先輩の口から聞かなければ分かりません」
若干先輩の声にいらつきが混ざったのを聞いてなお、私は押した。ふう、と明らかに聞かせるための音量で溜息が洩れて、だが優しい先輩は私を拒絶しなかった。
「…最後の手段だな。どうしようもなくなったときの」
書見台から顔を動かさずにぽんと発せられた声は、壁に跳ね返って私の耳に入った。語尾にはあきらかにこれで終わり、という頑なな語調があって、私もこれ以上は追及しない。喋っている内にも明るさの落ちてきた部屋、障子紙越しの斜陽。
先輩はそれ以来こちらを見ず、ただ巻物を手繰る小さな音だけが鼓膜をこする。
私は腹ばいの姿勢で、未だ先ほど手離したかんざしの前から動けずにいる。
触りはしない。だが私の視界に入るのは、その黒と朱色の簡素なかんざしだけだ。
私はこのかんざしの出所を知っている。
あれはもう一年近く前になるか。三木と町に降りて遊んでいた時に、立花先輩と同室の潮江文次郎を見かけたことがあった。
その日はたまたま市が立つ日で、往来は非常に込み入っていた。その市の端も端、怪しげな薬売りだとか大道芸だとかがいる辺りに、ござを一枚引いただけの露店で小間物やらちょっとした古道具やらを売っている店があり、そこに件の六年生はなにやら真剣な顔で座り込んでいたのだ。
手には、あのかんざし。
なにやら店主と値段の交渉でもしているのか、普段から良いとは言えない目つきがいっそう厳しくなっていたのをおぼえている。
勿論、見つけたのは三木であった。
その店の前を通り過ぎる時、ぐいと彼は私の袖を引いてきて、無言で顎をしゃくった。
私たちはただ肩をこするほどに混んだ道を歩き過ぎただけなので、潮江先輩が私たちに気付いたとは思われない。だが、私が振り返ったその瞬間、天の配剤か何か知らないが不思議に人の流れが切れ、私は潮江先輩の持つかんざしを確かにはっきりと見たのだ。
何故、こんな些細なことを今の今まで覚えているかと言えば、学園で一番忍者している武闘派で無骨な潮江先輩とかんざしという取り合わせの奇矯さにつきる。先輩の脇を通ってからしばらくしても、三木の両目は黒い部分が零れおちそうなほどまん丸に開いたままだったし、実際その後私たちはあのかんざしの行く末について散々熱っぽく創造的な議論を尽くしたのだった。
その時はどちらも相手を納得させるに足る結論を出せずに終わったのだけど、二人の間でただ一つ終始意見の一致した点がある。
今日見たことは黙っていること。
別に、何が悪いと言う訳でもないのだ。
あの年がら年中鍛錬で鉄粉おにぎりを食べているような人だって、かんざしのひとつくらい買うのだろう。それで、好いた女子の一人にでもやるのだろう。私個人には未だ経験が無いし理解も湧かないけれど、好きあった者同士が贈り物をすると言う話はよく聞く。
そのことを私が級友に話したからって、何がどうなるというのか。ぺるしやの象が酔っぱらって空を飛んでいたとか、男が馬をまるまる呑んだとか、そんな荒唐無稽な話なわけでもない。二つ上の学年の先輩の恋路など、私にはそこらに落ちている蝉の死骸程度の興味しか湧かないし、おそらく周りの同級生も似たようなものなので、夕飯の時の気軽な話の種として披露してしまえばよかったのかもしれない。
だけど、あの時の潮江先輩の、鬼気迫るような真剣さが私を思いとどまらせた。
あの目つきは、私などの低俗な野次馬根性が夕飯のおかずにどうこうしていいようなものではない気がした。
それは、畏怖か。
潮江先輩には何か、これからしようとする選択如何によってはこの世が滅びるかというほどの重さがあって、私にはきっと一生、あれほど真剣に誰かを想ったりできないと直感の深い部分で感じとったフシがある。そうして、その重さが貴いものであるというのは、自分に成し得ない分ひしひしと感ぜられた。
二人でこの同意に達した時、三木は顔色の悪いまま仰々しく頷き、こうしてあの光景は二人だけが胸にしまっておく運びとなったのである。
そのかんざしが、ここにある。
その先端に、恐るべき毒を宿して。
じっと先輩の後ろ姿を眺める。巻物に集中しているのか、若干猫背気味になっている様子からして、しばらく振り返らなそうだ、と見当をつける。
もし見られたら、いかに優しい先輩とはいえこの部屋から追い出されてしまうだろうけれど。
そうっと、音がしないように細心の注意を払いながら、そのかんざしを二本の指でつまみあげる。ひんやりと冷たい。
髪に挿しやすく尖らせてある先端をニ、三秒観察すれば、若干周りと比べて変色を起こしているような気がした。それが毒によるものなのだろうか。
そうして、ほんの一瞬。
私の舌は冷たい鉄の上をなぞった。
見つからぬうちに、とかんざしを素早く、だが気をつけて床に戻す。
目を閉じて、舌に残るぴりりとした苦みを味わった。茶や内臓の苦みとは違う、いつまでも纏わりつく妙に甘いような苦みだ。
ちょっと舐め取ったくらいではいかに強い毒であろうとどうなるわけではあるまいに、そうして苦みのことを考えていると心の臓がきりりと縮こまって痛むような気さえしてくる。
私は毒物の事には明るくないが、これが直接突き刺さればきっともう助かるまいと思う。
この鉄の先端が突き破るのは、恐らく彼の人を捕えることになったどこぞの忍びの心臓ではあるまい。
かんざしなどという小さな道具が使えるのは正しく一度きりなのだから。
一度きりで確実に、ある苦境から逃れるためにこの凶器が使われるのは、ああ、考えたくも無い!
考えたくは無いのに、私の忌々しい想像力はまざまざと日に焼けない白い肌、そこへ黒々と突き刺さった黒鈍色の鉄を思い描く。それを握りしめる、色を失って青白くさえある指のさきの千鳥を想うと、私の舌はまた勝手に喋り出していた。
「ということは」
「なんだ、またか」
先輩はこちらを向いてくれない。
私の頭の中には、きらびやかな女装束に身を包んだ先輩がゆっくりと倒れ伏す映像が蜃気楼のようにちらついていて、聞こえている声はまるで私らしくなく上ずる。 「そのかんざしを、明日先輩は着けていくんですか」
こんなに切羽詰まった声は、私の声ではない。これではまるで、親に置いてかれようとする、無力で無能な幼子ではないか。
「あのな、綾部、」
細く息を吐き出して、先輩は膝をずらして体ごと振り返った。先輩が見た私の表情など、先輩と天の神以外は恐らく一生知り得ないだろう。
「大丈夫、心配するな。これを使うなんてことは明日の内容なら万に一つもあるまい。これはただ…保険みたいなものだ」
「…」
「な、だから、そんな顔をしてくれるな。ちゃんと、帰ってくるから」
先輩を困らせるのは本意ではなかったので、ただ私は頷いた。たとえ頭の中でめくるめく悲劇が上映されていたって、先輩の忍務遂行能力に対しては一点の疑いも無い。別に、先輩が帰ってこないかもしれないなんてことを心配しているわけではない。
ただ。
ただ、視界を埋め尽くすように広げられた、美しいばかりの衣々の中に、そのかんざしがあると言う事実が私の心をひどく揺さぶる。
完璧に装って道を行く、むし垂れ衣姿に止まる千鳥の嘴が、私の一番ひとらしい部分をしきりにつつく。
だけどもそれを説明する事は口下手な私には到底できそうにも無いことであったので、物分かりのよいふりをして無言でうなずくほかは無い。
納得したと思ったのか、先輩は小さく頷き返してまた書物に戻る。だんだんと暗くなる部屋の中では、先輩のいる壁際は特に沈んでいて、深緑色の装束の色など土壁の陰さに同化してしまっているようだ。
私は腹ばいの姿勢から起き上がり、膝を曲げ、その膝を抱え込むように座りなおして障子の方を眺めた。
斜陽に染まった障子紙は、よく熟れた柿の暖かな朱色だ。壁一面に広がるただ一色の鮮やかな朱を、黒い桟が直角に仕切っている様子はとても美しいものであった。そして、それを見つめる私の両目にもその美しい光景が一杯にうつりこんでいるのだろうけれど、奥はぐろぐろと濁って渦巻いている。
外の強烈な熱を持った明るさと反比例して、彩度を失っていく薄暗い部屋の中、小指の先ほどのざくろ石がてらりと光る。かんざしなど薄っぺらいものであるのに、限界まで低くなった日のおかげで、その影はぐんと伸びて板間にひと際黒く染みを作っている。
さて、こうして中央に縮こまる私の影は、先輩まで届いているのだろうか。
口に含んだ苦さはまだ舌に残っている。
「ねえ、先輩、先輩」
彼の人の名を呼ぶ。この祈りは、身勝手である。
「そんなことは止してくださいね。悲しみます」
しおえせんぱいが、と聞こえないように付け足した声音の、我ながらなんと感情のこもっていないものか。
しないよ、と返ってきた声は、とてもとても優しいものであったのだけれど。
もう日が落ちる。そうすれば夕食の時間になり、私と先輩は連れ立って食堂に行くだろう。そこで私は同級生と、先輩には先輩の同級生と座ることになって、私たちは何も特別な儀式も無く日常の延長のままに別れるのだろう。そのまま私は自分の長屋に戻り、もう互いに顔を見ることも無いまま、次の朝早く先輩は実習に出かける。
別段、何が特別なわけでもない。
先輩の居ない委員会は今までも何度もあったし、先輩にとっては明日もいつものような「お使い」の一つにすぎないのだろう。だけれども、私の側の、先輩が実習に出かけると言うことについての認識は今日を境に決定的に変わってしまった。
私は先輩についていけないが、その人の結いあがった髪の毛には常にあのかんざしがある。潮江先輩のかんざしが。
秋がひとこいしいとは、こういうことを言うのかと知った。
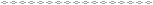
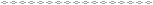
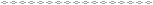
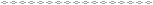
6い祭に投稿させていただきました。