葛の葉
「ねぇ、仙蔵って尻尾無かったよね?」
ぼたぼたと大粒の雨が板張りの屋根に響く夜長であった。
同室の少年がそんなことをいきなり言う出すものだから、夢境を半睡半醒で気持ちよくさまよっていた留三郎の意識はむりやり引き戻されてしまった。だが、目を開けたとて燈明を消した部屋の中は真っ暗だ。
「は?」
声が変わりきっていないせいで、素っ頓狂な高さが出る。
「いや、だから尻尾。生えてないよね?」
「…立花に?」
「うん」
「んなわけあるかよ」
不運が過ぎて頭に風邪をひいたのだろうかと呆れた留三郎は、寝入りの気持ちよさの余韻が冷めぬうちにと、しっかり目をつぶる。
そこへまた。
「仙蔵はさ、狐だって」
「え」
果たして自分は本当に起きているのだろうか。もしや、これはすでに夢の中なのではあるまいか。一年の時から伊作とは相部屋だが、そんな訳のわからないことをいきなり言いだすような質ではなかったのだけれども。
返答に疑念と不機嫌さが滲み出ていたのであろう、伊作が慌てたように付け足した。
「いや、僕だって信じているわけじゃないけど。…今日、四年生が噂しているのを聞いた」
「噂って、その、立花のことか」
「うん」
もうこうなったらしばらく眠るのは諦めた方が良さそうだ。ままよ、と目を開け、柔らかな眠気の残滓がこぼれおちていくのを少し惜しみながらも身を起こす。半身をひねって隣を見れば、闇の中にうっすらとうずくまる伊作の影があった。どんな顔をして言っているのか睨んでやっても、いまだ三年の彼に惜しいことながらそこまでの夜目は聞かない。
「その、奴が…狐?」
「そうなんだよー。ほら、委員会でさ、保健室行ったら四年生の先輩が二人だらだら喋りこんでて。大した怪我でも無いくせに、実習休めるーとか思ってるんだよきっと。保健室は休憩所じゃないのにね」
治療が終わったのならとっとと帰ればいいのに、邪魔でしょうがないんだなどと、ぶつくさ伊作はこぼす。さすがに上級生に面と向かっては言わないが、彼も色々溜めるらしい。
「四年、てそういえばい組が二学年合同組んで実習したって聞いたな」
「そうそれ、どうやらその四年、仙蔵の班にやられたらしくてね。あ、実習の内容聞いた?」
「いや、詳しくは聞いてない。なんか、旗取り合戦だと何とか」
そうそう、それ。と伊作の頭らしき黒い丸いものが頷いて、だがしかし体は起こさないままでこちらに寝がえりをうった。
上半身を支えていた腕が疲れてきたので、留三郎もばふん、と音を立てて自分の布団に背中から落ちた。二人揃って暗いだけの頭上を見上げれば、ぐずぐずと降りやまぬ雨の滴がどうしてそのまま天井板を突き破って畳に落ちてこないのか、不思議なくらいだった。他に何も聞こえぬ雨の夜であった。
「四年が一人一つ旗を持ってて、それを三年生がもぎ取るって課題だったらしいんだ。それで仙サマ、大活躍だったらしいよ」
「個人戦か」
「それは自由。組んでもいいらしかったけど…ま、決まってるよね。仙蔵のことだし」
うん、と留三郎も同意した。クラスは違っても、立花仙蔵と言う同級の出来の良さ、というか暴れっぷりはよくよくは組でも夕食時の話題になるところであった。
「独りで好き勝手に旗狩りねぇ。いかにも好きそうだな」
「ね、まあそんなわけで伸び伸びと暴れたわけだ」
「うん、想像つく」
「そうそう、それでまあその四年はこてんぱんにされたらしいんだよね」
「立花仙蔵にか」
「仙蔵に」
そう言う伊作の言葉の端にちらりと同情めいた響きがあったが、だがそれはすぐに共犯者のひそやかな笑みに変わる。普段いばり散らす上級生が、彼らの同期にのされたとなれば、これは痛快な話だ。
「で、その二人が僕を見て言ったんだけど…」
『おい、そこの三年。立花仙蔵というのがお前の学年にいるだろう』
『いますけど、それが何か?』
四年生とはいえ、保健室にだらだらと居座っていること、薬棚の整理をしようとする伊作の邪魔をしていること、それに何より、同朋について「立花仙蔵というの」という言い方が気に食わなかったことで彼の返答は少々尖ったものになった。だが、その四年はそんな無礼を咎めるでもなく、わざとらしく声を潜めた。
『あれには気をつけた方がいい、正体は狐だともっぱらの噂だ』
『ぼんやりつるんでると、誑かされるぞ』
『そうだ、何せ不運の保健委員会だから、格好の餌食だ』
険しさを増す伊作の視線にも気がつかないまま、その二人組は散々放言し、そして大仰に巻かれた足首の包帯の存在意義を問いたくなるくらい闊達とした足振りで、保健室を出て行った。
「て、どう考えたって悔し紛れに嫌がらせを言い触らしてるだけじゃねぇか」
とりあえず留三郎は突っ込んだ。すると伊作は口を尖らして、
「だから、僕だってそんなんで信じてないってば。…でさ、念の為後から来た委員長に聞いてみたんだ」
『先輩、あの、ちょっといいですか』
この伊作の問いに、深緑の制服を着た委員長が少々警戒しながら振り返った。伊作がそうやって一呼吸置いて何か頼む時は、大抵振り返るとろくでもない光景が広がっていることをよく承知していたからだ。それは広げてあった生薬の在庫帳が一面墨染になっていたり、畳中に細かな粉薬の粒が埋まっていたりする。六年のなかではぼんやりしているという評判の人であったが、泣きそうな伊作を慰めて、後片付けを毎回手伝ってくれるのはこの人だった。
ちらと走らせた目線が、畳は綺麗なままで硯もひっくり返っていないことを確認して僅かに安堵の色を浮かべる。それが伊作の見上げる両目と会い、
『どうしたの、伊作君』
『同級の立花仙蔵なんですが、さっき四年生が狐だって。そんな訳ないですよね?』
そりゃそうさぁ、またあいつら余計なことを言って、と即座に笑顔が帰ってくることを伊作は期待していた。ところが、
『え、何、聞いたの?』
と保健委員長の顔に渋面が浮かぶ。
『はい、あの、そこで座ってた四年生から…』
『あーあ、そこまで広まっちゃったか…』
『そんなの、でたらめですよね?』
なんだか煮え切らない委員長の態度に不安を感じながらも、畳みかけるように彼は聞いたのだが。
『…それを私に聞かれてもなあ。私も友達から聞いただけだから。…どうも、君らより上の学年の間で広まってるようだよ』
『え、でもそんなまさか、狐だなんて』
『そう思うだろう?僕も別段信じてるわけじゃないけどね。…でも彼の体格は独特だよね。男の子にしては骨が細いけど、それにしては筋肉もついてるし。やっぱり、人間離れしてるのかなぁ』
などと、聞かせるでもなくぶつぶつ呟くものだから、伊作の不安は高まった。
『先輩ー、どっちなんですか』
ついに袖を引っ張って回答を迫った伊作に、
『うん、保留ということで』
と、彼は満面の笑みで答えてくれたのだった。
「げ、まじかよ。六年生も?」
「ね?ちょっと気になるでしょ」
何故か伊作は満足げである。
「もっと色々聞かなかったのか?」
「それがさ、僕もそうしようと思ったんだけど、運悪く新しい一年の子が硯にけつまずいてさ、それどころじゃなくなっちゃった」
「ああ、結局…」
今度は本物の同情をにじませて、留三郎は遠い目をする。この場合、墨をぶちまけた一年と、続きを聞けなくなった伊作と、後始末をしなくてはならない委員長と、誰が一番不運なのだろうかと不毛な問いが浮かんだ。学年が変わっても、保健委員会にだけはなるまい。こうして誰もが不断の決心を固めるせいで、毎年押しつけられる羽目になる隣の級友に小声で詫びながらも、やはり決意を新たにした留三郎であった。
「あ、そういえば」
不運の錦の御旗を掲げて練り歩く保健委員会の図を押しのけて、留三郎の脳裏に浮かんだ光景がある。
「この前メシが遅くなった時に食堂行ったら立花もいてな、食べてたら廊下で四年生がコンコンって言って通り過ぎていった。俺もあいつもその時は意味が分からなかったから、普通にやり過ごしたけど。じゃ、あれはそういう意味だったのか」
「え、その四年って今日僕があった四年かな?」
「髷が短かったぞ」
「あ、じゃ別のだ」
「…てことは本当に広まってるんだな」
「うん、思いつきで言ったんじゃないみたい。それも四年生にねぇ…一二年が面白半分に怖がってるなら分かるんだけど」
何となく会話が途切れて黙り込んでしまった二人の上に、押し被さるように雨音がひっきりなしに響く。湿気を吸ったか、それとも気のせいか、暖かなはずの綿入れの布団がしっとりと重い。
彼らを外界から隔ち、守ってくれているのは障子一枚と、隣の会話まで聞こえる薄い土壁でしかないと思うと何とも心細いような気がした。夜気を含んだ空気が、どこぞの隙間から入り込んで留三郎の鼻先をすうっと撫ぜていく。
「ね、仙蔵って確か、実家が都の方にあるとか言ってなかった?」
「都の…そうだっけか」
「そうだよ、それも伏見」
伊作の、留三郎のよりも一段と高い透明な声が留三郎の予感を裏付ける。
「…いや、まさか。ただの偶然だろ」
「だよねぇ。伏見だってお稲荷さんばっかり立ってるわけじゃないんだし」
笑って返す自分の声が、ほんの少し上ずっているような気がした。
「でもね、言われてみて思い出したんだけど」
「まだ何かあるのかよ」
「前に女装実習した時、あからさまに本名と近いとよくないっていうんで、偽名を考えさせられたじゃない?」
「あー、あれか。お前はなんだっけ?妹子?」
「それは三年ろ組七松小平太の。…大体、名乗る前に同級の長次が止めてたよ」
もし表情が見えていたのなら、鼻に皺をよせて見せる伊作が見えただろう。更にもう少し明るければ、あからさまに不愉快気な口調とは裏腹のきらめきがその双眸に見えていただろうが、とりあえず留三郎は耳に頼るしかなかったのでこれ以上妙な名前を出すのは控えた。
「で、仙蔵は玉藻」
「…玉藻御前?」
その名を出せば、心なしか部屋の暗さが一段と増したような気がした。今は昔、鳥羽上皇に仕えた絶世の美女にして金毛九尾の妖狐は、正体がばれると那須に下り人を喰ったという。調伏されてからもその怨念は凄まじく、毒気を発する殺生石となって近づくものを片端からあの世に送っているというその伝説は、恐ろしい怪談として昔聞いたことがある。
「あとさあとさ、町に降りる街道の傍に、農家があって黄色い大きな犬を飼っているじゃない?」
「ああ、あの犬な」
その犬は気性が荒いことで生徒の間では悪名高く、彼らも一年生の時は傍を通るたびにびくびくと足音を潜めたものだった。だがもう大概に年を取ったのか、最近では吠え掛かりもせずに日がな一日小屋の中で大人しく余生を送っているという。
「この前合同演習の帰りにあの犬小屋の傍を通ったんだけど、僕たちは何でもなかったんだ。それがね、仙蔵が横を通った瞬間、もう吠えるのなんのって。夜盗が入ったってかくは吠えまいってぐらいの勢いでさ、つい振り向いちゃったよ」
「…何が言いたい」
「狐と犬って昔から仲が悪いものって決まってるんだってね」
でんでろとでも効果音をつければよかったのだろうか。妙に芝居が掛かった口調で伊作が申し渡す。
「そういえば仙蔵稲荷ずし好きだし」
偶然だろ、とは何となく言いづらい雰囲気になっていた。
「嫌なこと思い出した」
「え。それ言わないでいいよ」
「一ヶ月くらい前の、新月の夜にな」
「言わないでったら!!」
ぎゃあぎゃあ騒ぐ伊作を無視して話を進めたら、枕を抜かれた。布団があるとはいえどごく薄いものなので、鈍い音とともに後頭部が板間の感触を思い知る。
「…っお前な」
手を伸ばすと、片腕で宙に吊られていた枕に指先が触れた、ので即座に奪い返す。
「だって黙らないから」
むくれた声で伊作が言った。
「まあ、聞けよ。俺だってこんな話一人で抱えてるの嫌なんだから。それでな、新月の夜あいつとすれ違ったんだけど…」
「何ー?!」
言うなと言いながら、伊作は布団に潜るでもなく耳をそばだてているらしい。存外にはっきりした声であった。
ふと夜中に目が覚めた留三郎は、それからなかなか寝付けないので水でも飲もうと庭へ出た。
忍ぶには格好の、朔の夜であった。近頃段々と夏に向かいつつあって日中はじっとりと汗ばむような陽気であるが、この時刻になると過ぎ去ったはずの季節がひそやかに舞い戻らんと機をうかがっているかのように、気温がぐっと下がる。雑草の伸びつつある地面に立てば、夜着からむき出しの足元を撫ぜながら、ひんやりとした風がまとわりついた。
井戸は庭を横切った隅の方にある。
厠が近いので、鼻の奥底をきゅっとつまむような特有の生のにおいが流れてくる。まだ本格的に暑くは無く、言ってみれば生活の中常にある臭気であることから慣れもあって不快というほどではない。
踏み出すごとにさやさやと草ずれがする。音と言えばそれだけだ。
星明かりだけを頼りに井戸まで行き、釣瓶を使って水を汲み、手に受けて飲む。井戸の底に釣瓶が当たって、かーんという好い音が深夜のしじまに響きすぎるくらい響いた。飲みこぼした水が一筋、喉を伝って襟元を濡らす。数分もすれば乾くであろうその湿り気が、今は妙に冷たく感ぜられた。
と、耳が気配を捉えた。
動物にしては大きい。
忍たまのならいで瞬間に全身を緊張させた留三郎にお構いなしに、その気配はずんずんと近づいてくる。だいぶ近いであろうに、はっきりとした足音は聞こえないことから、少なくとも下級生(もしくは小松田さん)では無いらしかった。
そして、闇夜に人の形が凝る。
猫を思わせる細身に、まっすぐな長い髪。知らず、あ。と留三郎の声が漏れ出た。
「食満か。…寒いな、今夜は」
青白い仙蔵の面がぼんやりと後はただ暗いばかりの影に張り付いている。表情を見るには暗いが、いつもの紅い花のような笑みが灯っているのだろうと思った。
「ああ」
ほんのわずかな言葉を交わせば、後はただ喋る用も無いので留三郎は自室へと足を向け、仙蔵に井戸を明け渡す。
彼ら二人がすれ違うその刹那、下ろしてある仙蔵の髪の束がそよかに煽られて留三郎の鼻をかすめた。
それはぷうんと、獣の臭いがした。
「え、それ本当?」
「ああ、確かにあれは何か動物の臭いだ。こう、生物小屋の近くで嗅ぐような…いや、違うな、もっとあれはこう、野生っぽい感じだった」
「でもさでもさ、仙蔵だってそれこそ何か生物小屋に用があったのかもしれないし!」
「夜中に?」
「う」
「立花だぞ」
「うー」
獣遁の術は必須科目であるし、勿論何事にも手を抜かないかの友人はその辺りもきっちり履修しているのだが、どちらかというと相性が悪いようだった。「子どもと動物は話が通じない」とこぼしていたのを見聞きされている。
それであるから、用が無ければ生物小屋になど寄りつかないだろう。
「…てことは、もう留さんは信じているんだね?」
「え、いや信じてないぞ」
まだ、という条件を危うく呑み込んで、留三郎は首を振る。と、ずずいっと伊作が顔を寄せてきた。
「じゃあその夜の出来事はどう説明するわけ?」
「ぬっ…」
言葉に詰まったところで伊作が満足げな息をフフンと漏らすので、
「で、お前は結局信じてるのかよ」と逆襲してやった。
伊作はうーん、とか、あーとか散々言いあぐみ、
「…いやだってほら、不可能を除いて行った先にあるのが、いかにあり得なさそうに見えても真実だって、ホームズも言ってたし」
「誰だよ」
そうして何となく二人黙って、雨漏りのしそうな天井を見つめていれば、どこからか獣の遠吠えが聞こえてきた。この雨夜をしのぐ場所が見つからぬのか、それは腸を細くよじり合わせるように長く長く、悲しげな響きであった。
留三郎は人の熱で温い布団に一層深くもぐりながら、しとどに濡れた狼の白銀の毛皮と、吠えるたびに高く掲げられる美しい鼻先の流線を思った。
「仙蔵がさ、もしもだよ。信じてないけどたとえばの話、本当に狐だとしたら」
遠吠えの小さく遠くなる尾にかぶせるように、伊作がぽつりと言う。
「正体がばれたらやっぱり学園を出て行ってしまうと思う?」
「…そうなるだろうな」
三年も終わりに近づくころから、休みが終わっても学校に戻ってこない級友がちらほらいるようになった。張り合っているとはいえどこか圧倒的な違いを感じさせる四年生の、人数は三年よりずっと少ないのである。
「これ以上僕らの学年の人数が減るの、嫌だなぁ」
「ああ」
「この話、僕は留以外にはしない。うん、誰にも言わない。だから留さん?」
そうして、留三郎の肩のあたりの布が物言いたげに引っ張られる。
「…じゃ、俺は忘れたことにしておくか」
うん、と返ってきた返事は柔らかく、自分をこの寒々しい夜から守る綿入れの布団の手触りに似ていた。話したことなど碌にないい組の立花仙蔵に義理も借りも無いが、こうして級友が夜目も聞かぬ闇の中で笑っていられるなら、口を噤んでおいてやってもいいか、と思うのである。外は雨、部屋には隙間風だが、並んで敷かれた寝床二枚分だけはじんわりと他の何物でもない自分たちの熱で温もっている。
「寝ようか留さん」
「おう」
そうして眼を閉じれば、瞼の奥にちらちらとして白いものが踊る。それはあの夜中に見た級友の薄白い面であり、独り在っておめく獣の毛並みであり、雲の向こうにあるはずの月の丸さなのだ。とはいえ、本当にこの押しかかるような質量を持った鉛色の雲の奥にいつもの清かな月があるのかどうか、問われて是と答える確証はないのだったけれど。
留三郎はそのうち、いつ果てるとも知れぬ薄野を彷徨っていた。薄明るいだけで色の抜けきったぼんやりした空が広がり、そこかしこに鬼火が灯っては消える。足のつかれようからして随分長く歩いているのだが、行けども行けども景色は変わらない。
彼以外に人の気配は絶えてない。
不安に駆られ振り返れば、仙蔵に似て澄ました顔をした白い狐が、けっけっけと高く啼きながら横を走り抜ける夢であった。
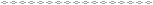
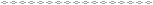
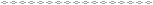
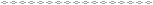
六年生は悪ノリだったと思われます。室町時代は妖怪を信じられる時代!
三年までは低学年。家の事情でやめていく子もいるけど、大体まだ揃ってる。
→四年になって授業激化。体力的かつ精神的にもハードになるので、脱落者続出してクラス合同授業が多くなる。
→い組とは組の面々が仲良くなるのは四年になってからかなという設定。
おまけ。一年後↓
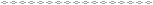
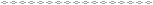
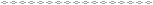
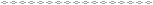
ようやく仲良くなってきた六人が、夏休み直前に庭先でだらだらしてる様です。
「そういや仙蔵、今年の夏は帰るのか」
「んー、そうだな。節目だし、帰るか」
「え、仙蔵帰るの?!」
「本当か!」
「え?あ、ああ」
「何でだ?バレたのか?!」
「帰っちゃやだよー!」
「…なあ、文次郎、この流れ何だ…?」
「さあな」
「文次郎も文次郎だ、同室として庇ったりはしようとは思わないのかこの薄情者めっ!」
「え、俺」
「仙蔵が狐だろうと何だろうと、僕は気にしないから!大丈夫だから!」
「そうだっ!そんなんでお前を追い出すような奴は逆に叩きだしてやる!」
「は?」
「おい、伊作泣くな、留武器しまえ」
「仙ちゃんって狐だったのか!」
「こへ…そ…は」
「そいつは大変だ、私も留三郎を手伝うぞ!」
「小平太乗るんじゃねぇ!!」
「待て待てお前達…。勘違いしてないか?私は普通に人間だぞ?」
「「「え、そうなの!?」」」
「そうだとも。文次郎や長次に聞いてみろ」
証言者1・潮江文次郎
「立花仙蔵はれっきとした人間だ。人間にしては性根がねじ曲がってるが…っをい!あぶね―な仙蔵。大体もしコイツが狐だったとして、四年間も同室してて気がつかないと思うか?」
証言者2・中在家長次
「人間だ…たぶん」
「たぶんてなんだおい」
「…証拠が無い」
「ほらやっぱり!」
「小平太、目輝いてるねー」
「だって長次が分からないって言うんだから、まだ決まったわけじゃないだろ。鈍感文次郎の証言は当てにならん」
「鈍感とはなんだ」
「お、やるかモンジ、受けて立ってやろう!」
「二人とも座って!」
「駄目だ、あれは止まらん」
「楽しんでるだろう、長次」
「…」
「ああーもう、誰が手当てすると思ってんの!」
「馬鹿はほっとけ。それより、本当に人間なんだな?」
「何回言わせる、私は人間だ」
「なんだー」
「残念そうな顔だな」
「え、いや全然全然」
「…一生の汚点だ」
「はっはっは、まさか四年にもなってンな可愛らしいことを信じてるとはな!」
「うっさい黙れ文次郎!夜中に厠行けなかった貴様が言うな」
「なっ、何年前の話だ!」
「だから座って二人とも!」
「文次郎、二度目やったら新作投げるぞ」
「なんで俺だけ!」